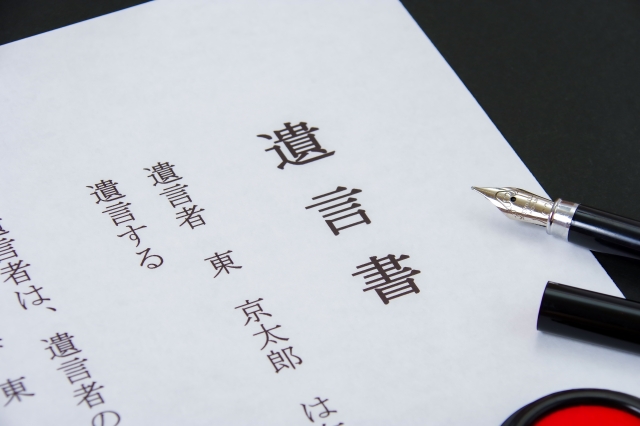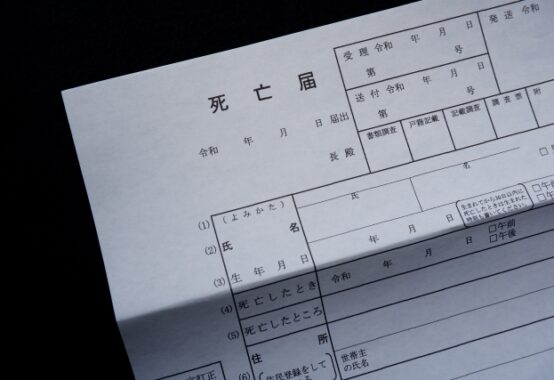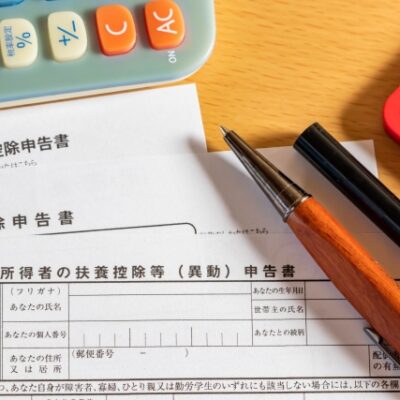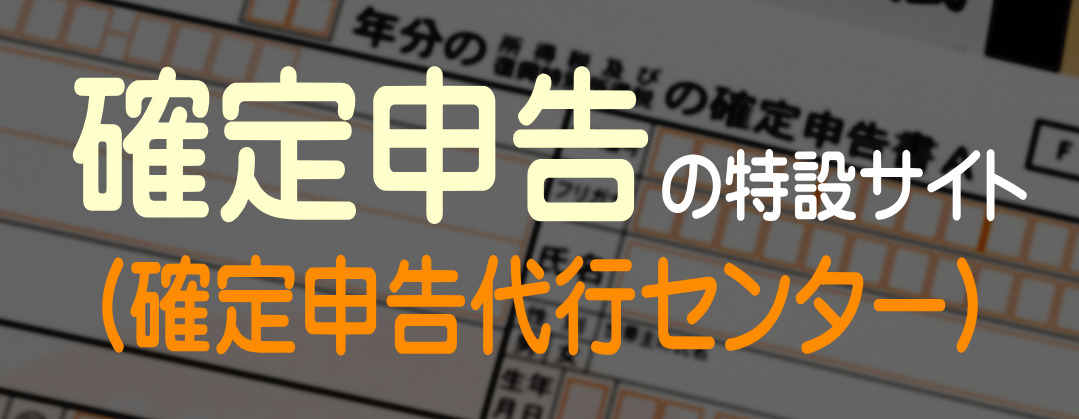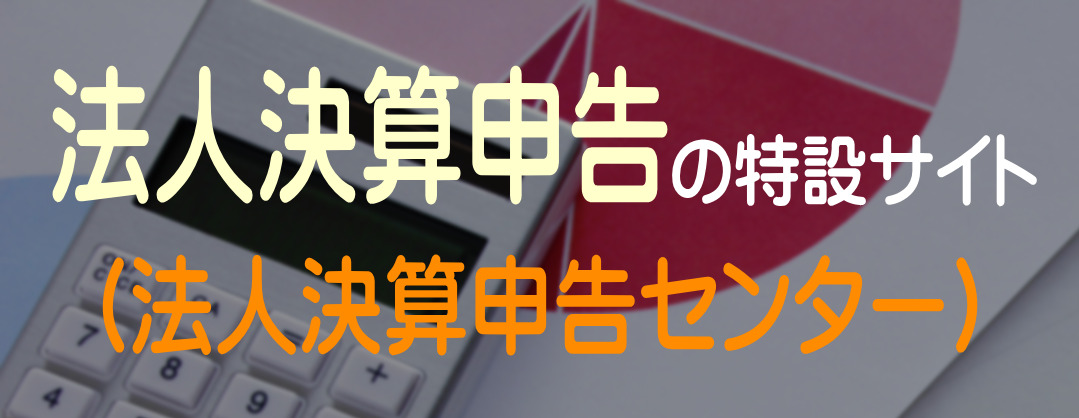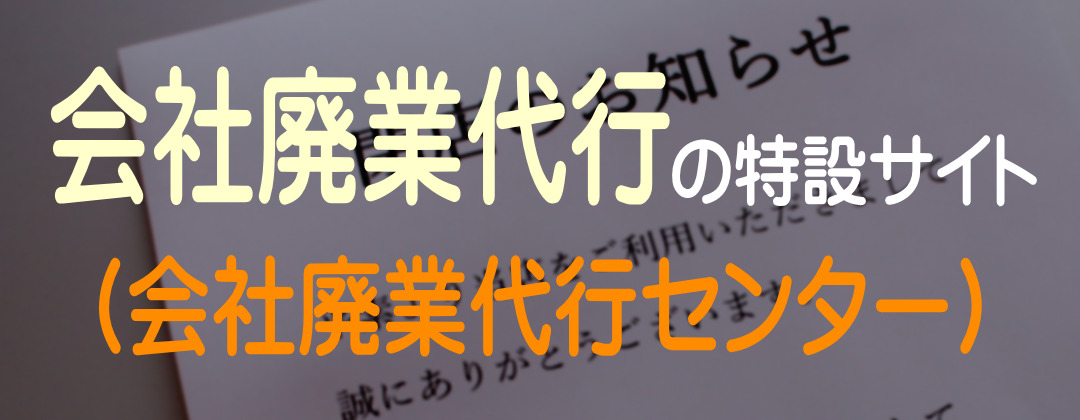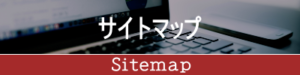万が一お亡くなりになったときに、その方の相続財産は、「遺産分割の割合」や「相続する順位・遺留分」などが、法律で定められています。
本人の意志で、自分の財産を「特定の人物」や「相続権のない人」に贈りたい場合などは、遺言書なしではできません。

遺言書とは
自分の死後、相続人同士の無用な争いを避けるために生前に自分の財産をどのように相続させるかを、書面により残しておくことです。
遺言書を作成しておいた方が良いケース
遺言書を作成しておいたほうが良いケースは様々ですが、下記に該当する方は、前もって作成しておきましょう。
- 自分で築きあげた財産なので、自分の意思で財産の配分を決めたい人
- 子供や両親がいない夫婦で、妻に全財産を贈りたい人(無いと兄弟が1/4の相続する権利が発生します)
- 相続権のない人(内縁の妻・義理の娘や婿・孫など)に遺産を相続してもらいたい方
- 世話になった知人や慈善団体に寄付をしたい方
- 自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい人
- 相続人同士の仲が悪く、自分の死後の相続でもめることを危ぐしている人
- 相続人が誰もいない人(無いと原則として国庫に帰属することになります)
遺産相続でもめないために
遺産の相続でもめるケースは、遺産総額の金額の大小は、実のところあまり関係ありません。
残された家族に対して、故人として遺産をどのようにしてほしいのか意思を伝えるだけでも意味があります。
遺産”争族”とならないためにも、自分の意思で自分の財産をどのように分けるか、生前に決めておきましょう。
遺言書にはどのようなことが書けるか
遺言書には、自由意志を実現させるためのものなので、どんなことでも書けます。
ただし、下記のような「法的に効力あるもの」と、書いたとしても遺族にそれを実行するように強制することができない「法的に効力がないもの」があります。
しかし、残された家族に対して「お母さんの面倒をみてくれ」などの法的に効力がないものであっても意思を伝えることにはとても意味があります。
法的に効力はあるもの例
| 内容 | 具体例 |
|---|---|
| 相続人の廃除等 | 道楽息子に財産を与えたくない |
| 相続分の指定等 | 家業を継ぐ子供へ分配財産を多くする |
| 遺産分割方法の指定と分割の禁止 | 長男は自宅を、長女には預金を与える |
| 相続財産の処分(遺贈)に関すること | お世話になった人に財産を与える 慈善団体に寄付をする |
| 内縁の妻と子の認知に関すること | 女性との間の子供認知する |
| 遺言執行者の指定または指定の委託 | 相続手続きを行う人(遺言執行者)を指定する |
遺言書の種類
普通方式と呼ばれる遺言書には、下記の3つがあります。
| 遺言書の種類 | 書く人 | 証人 | 作成方法 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人 | いらない | すべて本人の自筆( 【変更】下記の更新情報参照 |
本人が書いたものなのかなど死後争いになることがある |
| 公正証書遺言 | 公証人(口述筆記) | 2人以上 | パソコンやワープロなどの文書でも 可 | 法務大臣が任命した公証人の前で遺言書が口頭で述べた内容を筆記して証人とともに署名押印して作成する |
| 秘密証書遺言 | 本人(代筆も可) | 2人以上 | パソコンやワープロなどの文書でも 可 | 遺言の内容を秘密にできるが、証人と公証人には秘密にできない |
更新情報(2018年10月20日)
自筆証書遺言は、今まで財産目録などの添付資料も含めて、すべてを自筆しなければなりませんでした。
これが、2019年1月13日以降の作成分より、「自筆証書遺言の財産目録などの添付資料についてのみ」自筆でなくても良いことになりました。
これにより、「パソコンなどで作成した相続財産の目録」を添付することができるだけでなく、補足資料として「銀行通帳のコピー」や「不動産の登記事項証明書」などの添付も可能となりました。(ただし、添付書類の1枚ごとに署名押印が必要)
遺言書を作成するときに注意すべき遺留分とは
遺留分とは、残された家族への最低限の財産保証のことで、被相続人の全財産のうち、各相続人が最低限相続できる割合のことです。
したがって、複数いる子供のうち一人に全財産を相続させるという遺言書を作成したとしても、反対する人がいる場合にはその遺言書通りに実現するとは限りません。
例えば、相続人が配偶者と子供Aと子供Bの2人いる場合には、 少なくとも財産の25%を配偶者、12.5%を子供Aが、12.5%を子供Bが相続することが保証されています。
したがって、遺言書を書く場合には、相続財産の種類や金額を把握して、遺留分を侵害しないように書く必要があります。
もし遺留分を侵害した遺言書を書いた場合
侵害された相続人が承諾している場合
問題ありません
侵害された相続人が承諾していない場合
その相続人がその侵害された分を取り戻すための「遺留分減殺請求」という法的手続きを行うことになります。
遺留分の割合とは
法定相続人として誰がいるかにより、遺留分の割合が法律により下記の通り定められています。
したがって、確実に「遺言書で自分の意思により自由に処分できる部分」の割合というものは限定されてしまうことになります。
| 法定相続人 | 遺留分割合 | 全財産 | |
|---|---|---|---|
| 遺言書で自分の意思により 自由に処分できる部分 |
遺留分 | ||
| 配偶者のみ | 1/2 | 50% | 配偶者(50%) |
| 配偶者と子供 | 1/2 | 50% | 配偶者(25%)・子供(25%) |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 50% | 配偶者(33.33%)・父母(16.66%) |
| 配偶者と兄弟 | 1/2 | 50% | 配偶者(50%) |
| 子供のみ | 1/2 | 50% | 子供(50%) |
| 父母のみ | 1/3 | 66.66% | 父母(33.33%) |
| 兄弟のみ | なし | 100% | なし |
※ 割合が伝わりやすいように一部%表示にしてあります。
遺言内容を変更・撤回したい場合
内容を変更したい場合や撤回したい場合には、その遺言書の種類によって変更・取り消しの方法が違います。
| 遺言の種類 | 目的 | 方法 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 加入・削除・訂正 | 遺言書に書き込んで変更する |
| 取り消し | 破棄または遺言を撤回する旨の遺言書を作る | |
| 公正証書遺言 | 加入・削除・訂正 | 遺言を変更する旨の遺言書を作る |
| 取り消し | 遺言を撤回する旨の遺言書を作る | |
| 秘密証書遺言 | 加入・削除・訂正 | 遺言を変更する旨の遺言書を作る |
| 取り消し | 破棄する |
遺言書はいつまで有効?
結論から言えば、遺言書のものに有効期限はありません。
新しく遺言を作成しない限り有効となります。
公正証書遺言や秘密証書遺言の証人になれない人
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合には、「証人」というものが2人以上必要となります。
その場合の証人には、下記の人はなれないことになっています。
- 未成年者
- 遺言で財産を譲りうける人、その配偶者、その直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族
- 公証役場の職員など
- 遺言書の内容を読めない、確認できない人
したがって、遺言の内容が知られても問題のない第三者である証人が2人以上必要となります。
利害関係のない親しい友人や、守秘義務がある国家資格者(弁護士・行政書士・司法書士など) に依頼するのが無難です。
公正証書遺言を作成する場合にかかる費用
公正証書遺言を作成する場合には、下記の費用がかかります。
必要書類の取り寄せ費用
公正証書遺言を作成する際には、役所等で戸籍謄本、印鑑証明書、住民票、不動産の登記事項証明書などの書類を取り寄せる必要があります。
書類の取得費用は、戸籍謄本が1通450円、印鑑証明書や住民票が1通300円程度、登記事項証明書が土地・建物1つにつき600円になります。
公正証書作成の基本手数料
公証役場で公証人に支払う公正証書を作成する際の基本手数料は、公正証書に記載する財産の価額によって変わってきます。具体的には、次の表のようになっています。
| 相続する財産の価値 | 公証人に払う手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円ごとに13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円ごとに11,000円を加算 |
| 10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算 |
- 相続・遺贈を受ける人ごとに手数料を計算し、全員分の手数料額を合算して計算します。
- 全体の財産が1億円以下のときは、上記手数料に¥11,000を加算して計算します。
(参考:Q.法律行為に関する証書作成の基本手数料|日本公証人連合会)
作成手数料の計算例
例えば、公正証書遺言で妻に3,500万円長男に1,500万円相続させる遺言書を書いた場合には、妻の分(¥29,000)+長男の分(¥23,000)+1億円未満の加算分(¥11,000)=¥63,000が必要となります。
証人の日当
ご自身で友人などに証人になってもらえる人を探せば必要ありません。
遺言書の内容を他人に知られたくないなどの理由で専門家に依頼する場合には、公証人役場へ行く当日の日当がかかります。
遺言執行者は決めておいた方がいい?
遺言執行者とは、遺言者の死後に遺言の内容を実現するために必要な行為や手続きしてくれる人のことをいいます。
遺言書を書いたとしても、遺産が不動産である場合には相続登記手続きを行う必要がありますし、銀行預金についても名義変更手続きなどが必要となります。
遺言執行者は誰でも指名できますが、相続人の一人を指名すると親族間でもめることも考えられますので、利害関係がなくこれらの手続きに精通した専門家を指定することをお勧めします。
相続に関わってきて、相続人の方からよく不満としてよくお聞きするのが、法要費用を含めた葬儀費用や香典などのご臨終後のお金の使徒などが不明瞭で、喪主の方などの相続人の代表の方が隠しているのではないか?自分が立て替えた費用はくれるの?などのお話です。
このような相続財産に比べたら少ない金額のことが、相続(争族)トラブルの一因だったり、今後の親戚付き合いに思わぬしこりを残すことがよくあります。
突然訪れるご臨終でバタバタしている中で、銀行から葬儀費用などを引き出したとしても、法要戒名費用のほか心付けや飲食代などいろいろな出費が次から次へと発生します。
その後も、葬儀費用や病院費用などの支払や公的書類の入手費用をはじめ、四十九日法要が過ぎてもいろいろな出費があります。
法律上は必須なものではありませんが、このようなちょっとしたトラブルの原因にならないためにも、「お亡くなりになってから落ち着くまでの数ヶ月間の家計簿のようなもの」を作成しておくことをオススメします。
(当事務所では、このようなことにならないように、収支を記録した相続時の現金管理表の作成をオススメしております)
投稿者プロフィール

-
盛永崇也(東京神田で開業している税理士・行政書士事務所の代表)
「税務相談・税務顧問や経理経営支援・法人申告・確定申告・給付金申請・相続手続の代行・法人設立や廃業支援や代行」など、法人個人を問わず、お金にまつわる様々なサポートしております。